ホームページって作った方がいいの?ー前編
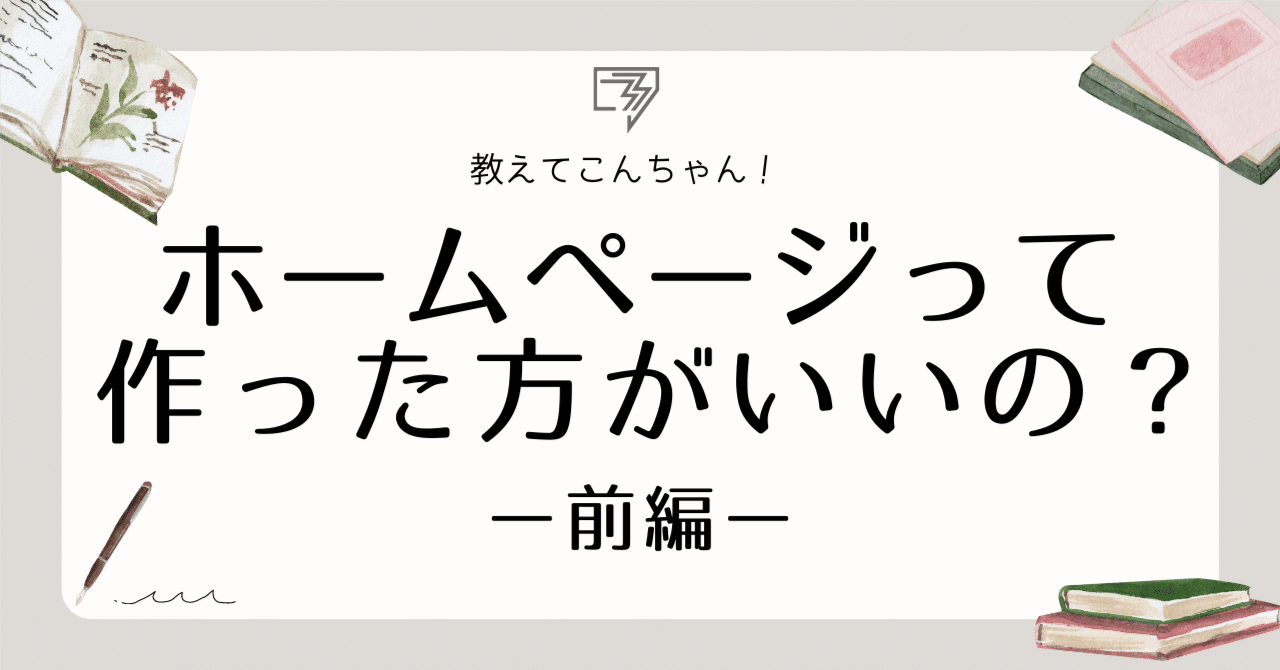
こんにちは。339PLANNING広報のEmikoです。
この記事では、SNSやWEBを使った広報について、気になることやわからないことを、社長の今野正輝(通称こんちゃん)に読者目線であれこれ質問し、皆様にわかりやすくお伝えしていきます。
今回のテーマは、
『ホームページは作った方がいいの?』です。
今は、いつでも、どこでも、誰でも気軽にSNSで発信できる時代。
もしかしたら、Instagram・Facebook・Twitterのアカウントは持っているけど「ホームページは作っていないよ」とおっしゃる事業主さんが多いかもしれません。
しかし、それで大丈夫なんでしょうか?
このあたりのことを、こんちゃんに聞いてみました。
SNSをホームページの代わりにしてもいいの?

Emiko:
最近はSNSを使って情報発信している事業所や店舗が増えてきましたよね。今やSNS全盛時代ですが、それでもやっぱりホームページはあった方が良いのですか?
こんちゃん:
はい。もちろん、あるにこしたことはないですね笑。
特に、これから新しく何かを始めようとしている人、物作りをしている人、ご自身の商品やサービスをお持ちの方や、ライターさん、デザイナーさんなどは、早い段階でホームページを作ったほうが良いです。
ちなみに、小さな会社やお店などで、情報発信用にSNSを利用している場合、そのSNSをホームページ代わりに使っているところがあると思います。発信する側にはSNSはとても便利なツールですが、その一方で、もしかしたら、お客さんは「欲しい情報はどこにあるのかしら?」と迷っていたり「どんなお店なのか?よくわからないなぁ…」と感じているかもしれません。
Emiko:
えっ?便利なはずのSNSなのに、大事なことが伝わりにくい…ってことがあるのですね。それはどうして起こるのですか?
こんちゃん:
SNSのアカウントは、どんなに仕事として使い分けているつもりでも「自分の頭の中にある情報」と「アカウントとして流すべき情報」がごっちゃになりやすいんですよ。
それに、SNSは書ける量が決まっているから、ついつい手っ取り早く「自分が書きたいこと」を書いちゃうんです。
すると「知らない人に向かって発信している」という意識がだんだん薄れてしまう。「相手(客)は自分のことを全く知らない」という前提が、頭からスッポリ抜け落ちちゃうんです。
結果「今日友達とこんなランチを食べました」とか「わたしのお気に入りのスイーツ」とか、空や風景の写真など、だんだん個人のアカウントのような発信の仕方になっちゃうんですよね。

Emiko:
気になるお店をネットで検索してみたら、そこはSNSしかやっていなくて、私が知りたい情報があまり記載されていなくてガッカリ…なんてこと、確かにあります。
こんちゃん:
その点、ホームページだと「自分が書きたいこと」をただ書いているだけでは、ページの全てを埋めることはできません。
というのも、ホームページの場合は、SNSとは逆で、内容を自由に構成できるし、たくさん書けるからです。
だから、ホームページを作るとなると、おのずと「空いているページを埋める作業」になっていきます。

で、「何で埋めていくか?」を真剣に考えたとき「相手(お客さん)は何を知りたいのか?」に、自分の視点がシフトするんですよ。
・自分のお客さんになってくれる人たちは、自分の何を知りたいのか?
・お客さんは何が気になっているのか?
・どうやったら自分に発注してくれるのか?
・どうしたら自分のファンになってくれるのか?
こんな感じで、視点を自分の外側に置いて、外から自分を観察するようになります。
Emiko:
「自分が書きたいこと」だけでなく「お客さんが求める情報」にも、意識が向くようになるのですね。
こんちゃん:
あと、SNSをホームページの代わりにするのが難しい理由は、SNSは最初からデザインが決められていて、自由に作り込めないスタイルになっている点です。
SNSは、すでにデザインなど型が決まっているから、その限られた型の中で、お客さんが迷うことなく「欲しい情報」にちゃんと辿り着けるよう「わかりやすい導線」を作らなくてはいけません。
これはすごく難しいことです。
その点、ホームページなら、自由に作り込めるので、見てくれている人に伝えやすくなります。

一見、SNSの方が自由に発信できるイメージがあるけど、実は、ホームページの方が、SNSと比べて圧倒的に自由度は高いです。
ホームページは配置や文字数や内容を自由に設定できるから、本当に伝えたい情報をきちんと載せられます。
「SNS」と「ホームページ」では届けられる情報が違う
Emiko:
「SNS」と「ホームページ」の違いを、もう少し具体的に教えてください。
こんちゃん:
はい。まず情報を発信する点では、SNSもホームページも同じ機能を持っています。
ただ、情報を「ストック」と「フロー」という、残すものと流れていくものという2つの視点で考えた時、SNSはフロー型のコンテンツになります。
SNSを使ったことがある人ならわかると思うのですが、ツイッターやインスタは、ストックする機能がものすごく弱いです。さらにTikTokだと、動画だけのフローが流れていく感じ。

Emiko:
確かに、SNSは手軽に発信できて便利だけど、載せていることは「その日のこと」「今のこと」が主流ですもんね。
こんちゃん:
ところが、ホームページは、情報のストックとフローの両方ができるんですよ。
ストックとして「仕事の実績」や「自分の経歴」なんかが載せられるし、また、フローとして「今こういうことをしていますよ」という情報もどんどん更新して載せられます。
情報のストックも実はとても大事なことです。
ストックがきちんと整理されて掲載されてあると、ホームページを見た人が「ここは、こんなことをやってきたお店なんだな」とか「こういう会社なんだな」と理解できて安心するんです。結果、それが信用につながっていくんですよね。

Emiko:
そういえば、ネット通販を利用する時、その店のホームページを必ずチェックします。ホームページのストック情報を見て、信用できる店舗かどうか確認していました。これは大事なことですね。
こんちゃん:
今はSNSのリンクにホームページを貼っておいて、お客さんにホームページを見てもらうのが「王道パターン」になっていますね。
ある意味、ホームページは「名刺」みたいなものかもしれません。
名刺がなくても仕事はできるけど、あった方が便利だし、何より、信用度が違いますもん。
ホームページを作るのは「家を建てる」ようなもの
Emiko:
ホームページとSNSの関連性について、もう少し教えてください。
こんちゃん:
例えばなんですけど、ホームページを「家」に例えると、「サーバー」が土地で、その上にある家(建物)が「ホームページ」で、家の住所が「ドメイン」になります。
これを更に「お店」で例えると、ホームページを開いた時に最初に出てくるページ(ファーストビュー)は、お店の看板です。
そして、ここでホームページとSNSとの関連性を考えたとき「SNSはどういう位置づけになるのか?」と言うと「SNS」はお店の棚です。商品を並べる陳列棚です。
店内の陳列棚だから、そこにどんな商品を並べるかは自由に決められるけど、棚ではこのお店のことをお客さんに説明できないし、商品のことも詳しく表現できません。

Emiko:
なるほど。そう考えると、SNSをホームページ代わりにしているところは、店舗を持たずに全国を回っている行商のおじさんみたいですね。
こんちゃん:
確かにそうですね笑。でも、SNSってスピード感があるから、リヤカーや車でゆっくり回るというより、イメージとしては、宅配ピザのバイクが近いかな。
Emiko:
バイクですか!ビューンと行っちゃうわけですね笑。
街角で宅配ピザのバイクを見つけて、気になって「ちょっと待って!」と声をかけても、バイクは走り去って行く…という。

こんちゃん:
自分の店に関心をもってくれたお客さんがいても「どうやって注文すればいいか?」がわからないと、次に繋がりません。
だからこそ「うちはこういうピザ屋です」という自己紹介や「こんなメニューありますよ」というご案内、「テイクアウトもやっているけど、ここでイートインもできますよ」の情報等をお知らせするツールが、配達バイクとは別に必要なんです。
この役目を果たしてくれるのが、ズバリ「ホームページ」です。
Emiko:
確かに、バイクで走り回るだけのところより、リアル店舗をしっかり構えているところの方が「そこに行けば、必ず欲しいものが手に入るぞ」という安心感がありますね。
【Emiko心の声🙄】
家と宅配バイクの例え話、すごくわかりやすかったです。
SNSとホームページの違いが理解できたし、ホームぺージの仕組みや良さがよくわかりました!
でも、いざ作るとなると、なんだか難しそうな気がします。どうやって作ればいいのかしら🥺?
次回は、ホームページについて、もう少し詳しくこんちゃんに聞いてみましょう。